JMASの歩み
| 2001年 9月 | 任意団体としてJMASを設立 |
| 同年 12月 | 第1回カンボジア現地調査 |
| 2002年 5月 | 東京都からNPO法人認定 |
| 2003年 3月 | カンボジア不発弾処理事業開始 |
| 2005年 9月 | ラオス事務所を設立 |
| 2006年 8月 | アフガニスタン地雷処理事業開始 |
| 2008年 5月 | 国税庁長官から認定NPO法人認定受ける |
| 2008年 6月 | アンゴラ地雷処理・地域復興支援事業開始 |
| 2009年 3月 | パキスタン水道改善事業開始 |
| 2011年12月 | JICA事業(アンゴラ専門家派遣)開始 |
| 2012年12月 | パラオ海中不発弾処理事業開始 |
| 同 | 防衛省事業(カンボジア能力構築支援)開始 |
| 2013年 3月 | アフガニスタン地雷処理事業終了 |
| 2015年 4月 | 東京都から認定NPO法人の認定を受ける。 |
事業実施の原則
JMASの事業は、定款第5条(事業の種類)に述べているとおり特定非営利活動に係る次の五つの事業を挙げています。地雷処理、不発弾処理、要員養成、技術開発、広報提言の五つです。
この中で、地雷処理事業及び不発弾処理事業が、当然、中心の事業であります。しかし、この両事業は、各種の制約や危険と誘惑を伴うために、時に停滞し或いは挫折消滅の危険性を内在する事業でもあります。
その為、予め事業実施の原則を次のとおり確立しました。
| 1 | 活動地域に治安の安全がある。 |
|---|---|
| 2 | 活動地域、国家が自助努力の意思を持っている。 |
| 3 | JMAS、日本に対して正しい理解が得られる。 |
| 4 | JMASの能力対応事業がある。 |
事業の検討と調査
地雷に苦しむ人々は、アジア、アフリカ及び東欧と広い地域に亘っている。
(下段の地域)
| アジア | AFGHANISTAN、TAJIKISTAN、CAMBODIA、LAOS、VIETNAM |
|---|---|
| アフリカ | ANGOLA、MOZAMBIQUE、SOMALILAND、ETHIOPIA、ERITREA、SUDAN |
| 東 欧 | BOSNIA、CROATIA、CHECHNYA、ABKHAZIA、NAGORNO、KARABAKH、KOSOVO |
活動について
主な活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救助活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
主な事業
- 地雷、不発弾及びこれらに類する爆発物の処理を支援・協力する事業
- 生活環境の改善を支援・協力する事業
- 処理要員の養成を支援・協力する事業
- 処理器材及び処理要領に関する調査、研究並びに技術開発の事業
- 機関紙、刊行物等の発刊、広報活動及び政策提言等の事業
- 文学、伝統文化、芸術等を振興・推進する事業
- 国際文化交流、外国語講座等を振興するのに必要な支援・協力事業
- 人権啓発・擁護活動及び平和の推進活動を支援・協力する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
JMAS支援活動の枠組み

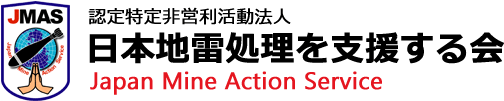

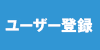




 JMASの歩み
JMASの歩み